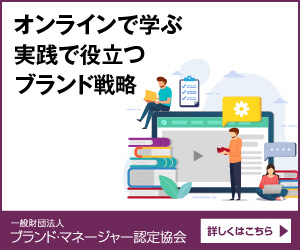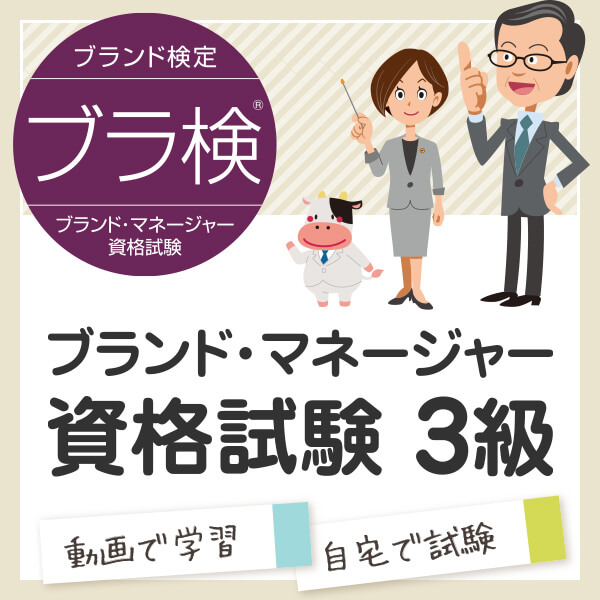ネット通販全盛の時代、リアル店舗を持つ小売業では「モノではなく体験を売れ」とよく言われますが、それを一大複合施設で実現させたのが東京・二子玉川の「蔦屋家電」です。同施設をヒントに、小売業の将来像について考えてみました。
書店を中心とした複合施設が人気
「ツタヤ(蔦屋)」(カルチュア・コンビニエンス・クラブが運営)といえばレンタルビデオのイメージがありますが、創業時から書店であり、現在は雑誌・書籍の売上では紀伊国屋書店を凌ぐ日本一の書店となっています。成長の理由の一つが、書店を中心としつつ、カフェやレストラン、ショップなどとの複合商業施設化が好調なことです。2011年に複合商業施設「代官山T-SITE」をオープン、そして2015年には「二子玉川蔦屋家電」をオープンさせました。「蔦屋家電」は毎年売上を伸ばし、現在では平日2万人・休日2万5000人が訪れるとのことです。
「蔦屋家電」は家電店ではない
あらためて「二子玉川蔦屋家電」に足を運んでみました。
二子玉川は渋谷から田園都市線で10分、アクセスのよさ、自然環境のよさから特に高所得者層が住むのに人気の新興住宅街として知られています。二子玉川駅前は高島屋や二子玉川ライズといったショッピングセンターが立ち並ぶ、一大商業地域になっています。そのライズの一棟「テラスマーケット」の1階900坪と2階1200坪を占めるのが「蔦屋家電」です
先に言ってしまいましょう。「蔦屋家電」といっても家電量販店にように家電だけが並んでいるわけではありません。それどころか、書籍・雑誌も、家具も、自転車も、玩具も、ソファも、CDも、化粧品も、観葉植物も売っています。スターバックスもファミリーマートもあります。蔦屋の他に、12ものショップが入居しており、複合商業施設です。
それにも関わらずフロア全体が一大セレクトショップのように思えるのは、フロア全体の世界観の一体化です。照明を落とし、観葉植物がところどころにおいてあり、落ち着いた音楽が流れるシックな雰囲気のなか、人々が気ままに商品棚や本棚を眺めて歩き、気に入った雑誌を手にし、ソファでくつろぎながらコーヒーカップを片手に雑誌を読む。
そんな体験がコーヒー代だけでできるのです。人気がでないはずがありません。

本は商品であり、インテリアであり、広告物である
書籍とカフェの説明から入ってしまいましたが、この施設の一番の特徴は、メインの環状の通路が「ブックストリート」と名付けられており、両側に本棚が並べられていて、本棚の雑誌を眺めながら各コーナーやショップを移動する動線になっていることです。
この施設の肝といえるのが、この書籍・雑誌棚と商品との連動です。例えばブックストリートを歩き「美容・メイク」「ファッション論」についての本棚に差し掛かり、美容についての本を眺めていると、本棚の向かいに美容に関しての家電や化粧水などが展示してある。
子育ての本を眺めているとその向かいに教育玩具のショップがある。音楽雑誌を眺めているとその向かいにCDやスピーカーのショップがある、という具合です。
つまり、書籍・雑誌が商品であると同時に、インテリアであり、ショップへ導くハブであり、広告物なのです。蔦屋だからこそできる店舗設計です。
ライフスタイルを売るショールーム
蔦屋家電は「ライフスタイルを売る家電店」と謳っていますが、まったくその通りだと思います。
あえていえば「ライフスタイルを提案するショールーム」といえると思います。書籍や家電に限らず、照明が、観葉植物が、ソファーが、店舗になじむように置かれていて、ここちよいライフスタイルを演出するアイテムとして提案されています。「モノを売る」というよりも、「ライフスタイルを体験してもらう」場であるといえます。
小売業界では「モノを売るより体験を売れ」とさかんに叫ばれています。ネット通販で何でも選べて、安く買える時代に、ただ商品を並べて、「安いよ安いよ」と謳っても、ネット通販には価格でも品ぞろえでも負けてしまいます。小売業はネットにない体験をしてもらう場にならなければならないとは散々言われていますが、蔦屋家電はそれを愚直に体現させたのです。
小規模店舗でも実現できる「体験の場」
「蔦屋家電」の店舗づくりは、規模に関係なく、小売業にとって大きなヒントになるでしょう。
例えば「村上春樹ショップ」を作るのはどうでしょうか。小さなミュージアムのような店舗に、彼の小説に出てくる音楽や絵画のレプリカを配し、彼の世界観を演出、そこでもちろん小説も売るのです。ファンによる朗読会を開いてもかまいません。村上春樹の小説を売る場ではなく、世界観を体験する場、コミュニティの場としてのショップを作るのです。
もちろん本人の許諾などクリアしなければならない問題はありますが、店舗の一コーナーとして作ることも可能です。また例として村上春樹を出したまでのことであって、三島由紀夫でも養老孟司でも誰でも構いません。
養老孟司が出てきましたので、脳科学をテーマとするショップ、SFをテーマとするショップ、インド哲学をテーマにしたショップ…いくらでもセグメントができるように思います。
蔦屋家電はライフスタイルを売る店という壮大な構想を形にしました。個人的には、テーマが大きすぎて、2100坪のフロアにおいても、消化しきれていない部分があると思います。テーマを絞って、商品のカテゴリーにこだわらず、そのテーマの世界観を演出する。そこに小規模の小売業の活躍の場があるように思います。