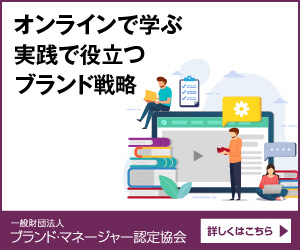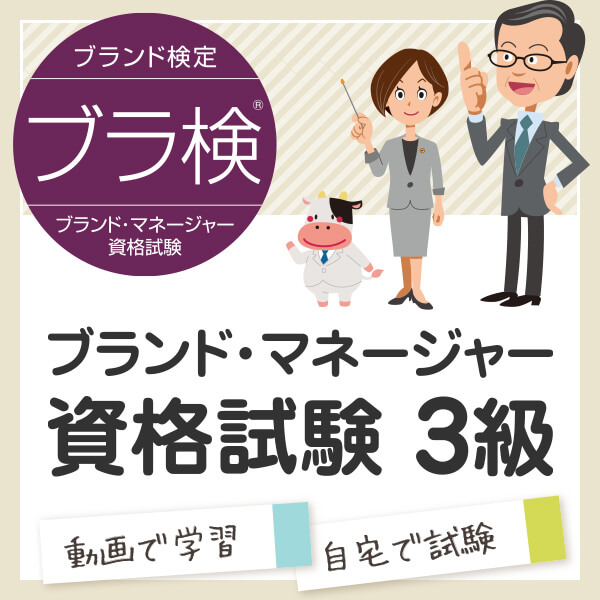「いい言葉」を壁に貼るだけでは、組織は変わりません。経営理念やMVV(Mission / Vision / Value)が社員一人ひとりの判断基準になり、日常の行動に結びついて初めて“理念浸透”と言えます。本稿では、日本企業を中心に実際に成果を上げている5社の取り組みを紹介し、共通する成功要因を抽出します。
LIFULL|理念を「言える」から「使える」へ。社員全員が“自分の言葉”で語る組織づくり
背景と課題
不動産情報サイト「LIFULL HOME’S」など、住まいにまつわる多様なサービスを展開するLIFULL。「日本一働きたい会社」「働きがいのある会社」として数多くの受賞歴もある1500名規模の企業ですが、急速な新規事業の立ち上げと中途採用の増加によって「利他主義」を核とする経営理念が社内で薄まりはじめた時期がありました。特に2010年代後半には「会社の理念に共感し、貢献したいと思っている」と答える社員が8割を切り、理念の“自分ごと化”が大きな課題となっていたのです。
取り組み
そこで同社は、理念の言語を“日常の判断基準”として機能させるための複数の施策をスタートさせました。その一つが入社後半年以内の社員を対象にした「ビジョンカレッジ」です。執行役員を講師として理念に触れ、対話を重ねながら社是・経営理念・ガイドラインを自分の業務と関連付け、より身近なものとして理解、行動につなげていきます。
さらに、年1回の筆記試験「LIFULLテスト」では、会社の理念・行動規範への理解を測定。結果は個人評価やキャリア面談にも連動しており、「理念が昇格・報酬に関わる」という本気度を社員に示しています。
加えて、すべての部署がビジョンを掲げることで「ビジョンツリー」を作成し、経営理念と部門目標、個人の役割を線でつなぎます。これにより“自分の仕事が理念とどうつながっているか”を常に意識できるようになっています。
成果と波及効果
2024年度には、理念に貢献したいという社員が 84.5% まで回復。加えて、経営陣が「理念を体現している」と評価した社員は 88.6% に上り、トップダウンとボトムアップの両輪で理念浸透が進んでいることがうかがえます。
理念が浸透している組織は、変化にも強く、部門横断的なコラボレーションも生まれやすい。LIFULLの取り組みは、理念=カルチャーの骨格であることを実証しています。
カゴメ|“理念の実装”は、働き方改革から。「開かれた企業」を行動で体現する
背景と課題
企業理念として「感謝」「自然」「開かれた企業」という3つの価値観を掲げるカゴメ。しかし、2010年代中盤には社内外で「理念と実態のズレ」が指摘され始めました。とりわけ、共働き家庭の増加に伴う“転勤できない問題”や、“働き方の柔軟性不足”は、理念の一つである「開かれた企業」との乖離を象徴するものに。
制度が追いついていなければ、理念は「掲げているだけの言葉」になってしまう。その危機感が、改革の出発点でした。
取り組み
カゴメは理念浸透を、“働き方そのもののアップデート”から着手します。まず実施したのは「地域カード」という制度の導入です。「東京から動きたくない」「東京に出たくない」といった希望に応えられるように勤務地を固定する選択が可能となり、パートナーの転勤に伴っての異動希望も申請できるようになりました。
さらに副業を全面解禁に。働き方の選択肢を増やし、社員一人ひとりの“キャリアの自律性”を尊重することで、理念の実装につなげています。
そしてユニークなのが、社内SNSを活用した「サンクスバッジ」の取り組みです。社員同士が日々の小さな“ありがとう”をバッジとして送り合う仕組みで、「感謝」を可視化し、自然発生的な理念の循環を生み出しています。
成果と波及効果
副業制度開始から3年、申請者の約6割が「本業へのモチベーションが高まった」と回答。エンゲージメントスコアも年々改善傾向にあり、「理念を語る」よりも「理念を生きる」組織文化が徐々に根づいています。
理念は“正しさ”を説くだけでなく、制度で選択肢を保証してこそ浸透する——。カゴメの取り組みは、カルチャー改革を支える制度設計の好例と言えるでしょう。
オムロン|理念を“共感の物語”に変える、38,000人参加のグローバルアワード
背景と課題
オムロンの経営理念は「われわれの働きで われわれの生活を向上し よりよい社会をつくりましょう」。社会課題解決を目指す理念ですが、M&Aを繰り返しながら急拡大した組織では、国や拠点ごとに理念の解像度がバラつくという課題に直面します。現場レベルでは「理念が立派すぎて、日々の仕事と結びつかない」「拠点によって理解度に差がある」といった声が上がっていたといいます。
取り組み
こうした課題に対して、オムロンが打ち出したのが「The OMRON Global Awards(TOGA)」。2012年からスタートした社内アワードで、世界中の社員が“理念に基づく挑戦”をテーマにエントリーします。
ユニークなのは、単なる表彰イベントではない点。TOGAでは、社員がまず「理念に沿った課題設定(旗を立てる)」を行い、その後、実践→振り返り→共感というサイクルを回していく、まさに“理念体験型プロジェクト”なのです。各拠点で選ばれた代表チームは、毎年5月の創業記念日に京都で開催される決勝大会でプレゼンを実施。その様子は全世界にライブ配信され、数万人規模で視聴されます。
成果と波及効果
2022年度は 6,930件のテーマ/50,000人超の社員が参加。TOGAで共有されたストーリーは社内SNSなどで拡散され、“理念実践の物語”が社員同士をつなぐコミュニケーションツールにもなっています。
一方通行の「理念教育」ではなく、社員が共感し合い連鎖する「理念共有」へ。オムロンは、理念を“体験”し、“語り継ぐ”文化をデザインすることに成功しています。
ニデック(旧日本電産)|冊子一つで世界30カ国を束ねる、哲学の伝播設計

背景と課題
「情熱・熱意・執念」で知られる創業者・永守重信氏の思想は、長らくニデックグループの原動力でした。しかし、M&Aを積極的に展開するなかで、企業文化の統一という壁に直面します。
拠点や国によって、理念の理解度や受け止め方にばらつきが生じ、「ニデックとしての一体感」が揺らぎ始めていました。
取り組み
同社が選んだのは、“創業者の哲学を言葉で残す”というアプローチでした。
永守氏の語録や講話を体系化し、12言語に翻訳した小冊子『挑戦への道』を制作。これを全世界の社員に配布し、研修や1on1の際に繰り返し活用します。
さらに、グループ共通の行動指針「NIDEC Way」を定め、行動評価にも直結。社員は評価面談の中で「どの行動が理念に即していたか」を自己申告し、上長と対話します。冊子と評価制度の両輪で、理念を“日常の判断軸”へと引き寄せているのです。
成果と波及効果
「会社の理念を日々の判断に使っている」と回答する社員の割合は、3年で 10ポイント上昇。研修時間の拡充やエンゲージメント向上にもつながり、買収先との文化融合においても基盤となっています。
ドキュメント一つが、組織全体の意思決定や評価にまで影響を与える——ニデックの事例は、理念を“言葉で残す”ことの力強さを教えてくれます。
ツムラ|対話を通じて理念を育て合い、醸成するカルチャーを作る。
背景と課題
医療用漢方薬のリーディングカンパニーであるツムラは、2000年代の経営不振や不祥事の反省から、「ツムラらしさ」を取り戻す必要性に迫られていました。
創業精神に立ち返った「社員一人ひとりの内発的な共感」が求められていたのです。
取り組み
同社は“一方通行の理念研修”をやめ、代わりに全役職員が参加する対話型の「理念浸透・コーチミーティング」を導入しました。経営理念や行動指針を一方的に伝えるのではなく、社員一人ひとりが自分の言葉で語り、対話を通じて深く理解することを目的としています。具体的には、理念の再確認を行った後、少人数のグループに分かれて対話セッションを実施。各自が日常業務で感じたことや経験を共有し、理念とのつながりを探求します。その後は、参加者同士でフィードバックを行い、自己の行動や考え方を振り返ります。
このプログラムの狙いは、理念の理解を深め日々の実践につなげること、社員間の対話を通じて多様な視点を持つこと、自律的に考え行動する人材を育成すること、そして組織全体の価値観や文化の醸成です。ツムラではこうした対話型の理念浸透を通じて、社員が理念を自分事として捉え、日常業務に反映できるよう促しています。これにより組織全体の一体感を高め、主体性を持つ社員を育て、企業の持続的な成長を支える基盤づくりを進めています。
この取り組みは、2019年に「ツムラグループの基本理念に基づいた経営を実践できる経営人財の養成および組織開発を行う」ことを目的とし設立された社内教育機関「ツムラアカデミー」と連動して運営されています。
成果と波及効果
年間の対話を通じて「理念が日々の判断軸になった」と答える社員は80%を超えました。単なるスローガンではなく、「一緒に育てるカルチャー」として、理念が組織に根を張っています。ツムラの取り組みは、「理念は育て合うもの」という考え方を体現した、まさに“漢方的”とも言えるアプローチです。
まとめ
企業理念は掲げるだけでは社員に届きません。実際の行動に浸透させるためには、「課題の見える化」「施策の仕組み化」「成果の共有」が欠かせない要素です。明日からすぐに始められる3つのステップを具体的に整理してみましょう。
【Step1】課題を“数字”で見える化する
まずは「今、何が課題なのか」を明確に把握しましょう。「理念が浸透していない」と漠然と捉えるのではなく、
・理念理解度サーベイのスコア
・従業員エンゲージメント指標の推移
・離職率や転職理由アンケートの結果
など、具体的な数字で現状のギャップを可視化します。「なんとなく」ではなく、数字で課題を示すことが、組織の共通認識を作り、施策への説得力につながります。
【Step 2】「体験」と「制度」の両輪を設計する
課題が明確になったら、それを解決する施策を設計します。重要なのは、理念を「頭で理解するもの」ではなく「体験するもの」に変えること。次の2つをセットで設計すると効果的です。
体験型の仕掛け:社員が理念を直接感じられるようなイベントやワークショップ、社内アワードなど、「共感や熱量を生む仕掛け」を用意します。
制度面の仕組み化:人事評価や昇格基準、副業制度や勤務地選択制度など、「日常業務の中に理念を組み込む仕組み」を作り、理念に沿った行動を継続させます。
この2つを組み合わせることで、「理念を行動に移し続ける」組織文化が生まれます。
【Step 3】効果を「見える化」し、成功体験をフィードバックする
最後のステップは、実施した施策の成果を具体的に見える化し、社内で共有することです。
・社内SNSで理念に関する成功エピソードを拡散する
・社内表彰制度を通じて良い事例を可視化し、社内のロールモデルにする
・定期的なサーベイで施策の効果を評価し、次年度の改善につなげる
「理念に沿った行動」が可視化されると、社員一人ひとりがそれを自分の物語として語りやすくなります。成功体験を継続的にフィードバックすることで、自律的な改善サイクル(PDCA)が定着し、組織にとって理念が自然な行動基準となります。
この3ステップを着実に踏むことで、理念浸透を進め、組織変革を進めることが可能になります。
理念浸透の第一歩である課題発見においては、理念の浸透度合いを「ブランド・エンゲージメント診断テスト」で数値化し、共通認識を持つのがおすすめです。
これは従業員の「ブランド体現度」×「エンゲージメント」をWEBでテストし、従業員にブランドが浸透し、仕事にイキイキと取り組めているかを診断。結果を踏まえて現状を可視化できます。
「ブランド・エンゲージメント診断テスト」の詳細はこちら
おわりに
理念は「語る」から「体験する」、そして「共有する」ことで社員一人ひとりの行動基準となり、会社の強力なカルチャーへと昇華します。「課題の定量化」「体験と制度の両輪設計」「効果の共有」という3つのステップを実践し、理念が「掲げるもの」から「生きるもの」へ変わる瞬間を体感してみてください。
CBOメディア&ラボ【ブランディング推進のための情報メディア】
【経営×ブランディングの責任者(CBO)を日本で増やす】経営に貢献する真のブランディングを広めるために、ブランドづくりの基礎知識・ポイントからさまざまな事例、そして実践的に学べるセミナー、相談会まで。幅広いメニューで社会にCBOを増やしていきます。
※一般財団法人ブランド・マネージャー認定協会公認
最新情報を発信しています。

■笠原 章吾(かさはら しょうご)執筆
クリエイティブディレクター・コピーライター