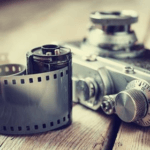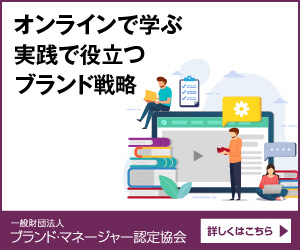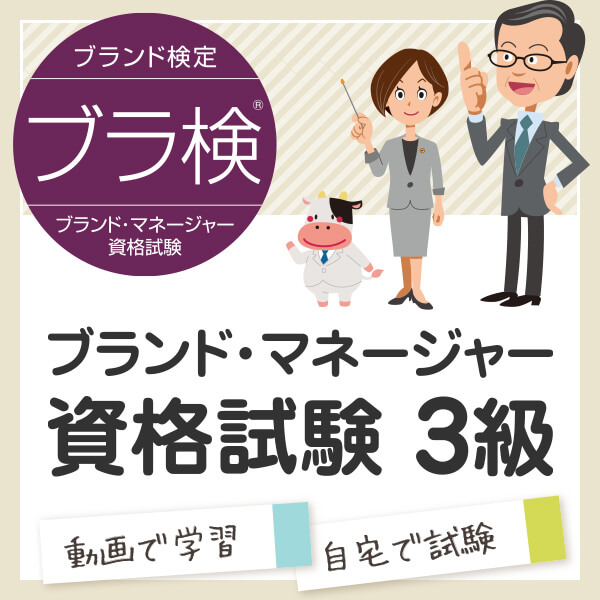三菱UFJ銀行とは
三菱UFJ銀行(MUFG Bank)は、三菱UFJフィナンシャル・グループ(MUFG)に属する日本最大級の銀行であり、世界有数の金融機関です。2006年に三菱東京フィナンシャルグループとUFJホールディングスの統合により誕生し、国内外で幅広い金融サービスを提供しています。個人・法人向けの預金や融資、資産運用、M&A支援、リスクマネジメントなど、包括的なソリューションを展開。約50か国・地域にネットワークを持ち、グローバルな視野で顧客のニーズに応えることを目指しています。
事件の概要
24年10月、信頼・信用という銀行ビジネスの根幹を揺るがす大事件がおきました。同行の元行員が約4年半に渡り、貸金庫に保管していた顧客資産を窃取していたことが明らかになったのです。2020年4月から2024年10月までに約60人が被害に遭い、金額は時価で十数億円に上ると報じられました。犯人は、支店長代理をつとめていた40代の女性です。支店の貸金庫や予備鍵の管理責任を務めていたという。スペアキーを不正利用し犯行をくりかえしていたところ、利用客から『貸金庫に入れていたものが減っている』と相談の連絡が入り発覚しました。
記者会見は、事件発覚から1ヵ月後
三菱UFJ銀行は12月16日、元行員による貸金庫の窃盗事件に関する記者会見を開きました。半沢淳一頭取は「お客さまに多大な不安を与えたことを非常に重く受け止めている」と謝罪し、管理体制に不備があったことを認めたのです。会見で経営責任を問われた半沢氏は「真因の分析や再発防止策の実行に取り組むことが最大の責任だ」とし、合鍵を本部で一括して管理するといった再発防止に取り組む考えを示しました。
今回の騒動を不正のトライアングルに当てはめてみると
不正のトライアングルとは
人が不正をする仕組みをモデル化した「不正のトライアングル」をご存知でしょうか。「不正のトライアングル」とは、米国の犯罪学者 ドナルド・R・クレッシーが提唱した経済犯罪学の中で広く受け入れられている理論です。この「不正のトライアングル」では、不正行為は1.「機会」2.「動機 (プレッシャー)」3.「正当化」の不正リスクの3要素が揃ったときに発生すると考えられています。
1. 機会
「機会」は不正行為が実行可能である状況や環境を指します。内部統制が不十分である場合や監視が甘い場合、不正が発生しやすくなります。例1: 小規模な会社で会計担当者が一人しかおらず、経費の水増し請求が容易に可能。
例2: 大企業でITシステムのログが適切に管理されていないため、データ改ざんが容易。
例3: 在庫管理がずさんな環境では、従業員が商品を持ち出しても発覚しにくい。2. 動機 (プレッシャー)
「動機」は、不正行為を起こす引き金となる個人的または組織的な圧力やストレスを指します。多くの場合、経済的なプレッシャーが主要な原因ですが、その他の心理的要因も含まれます。例1: 多額の借金を抱え、生活費や返済のプレッシャーから資金の横領に走る。
例2: 高い売上ノルマを課され、その達成が昇進や解雇に影響する場合、不正な売上計上を行う。
例3: 会社全体が業績悪化に直面し、経営陣が株主の信頼を守るために会計データを操作する。3. 正当化
「正当化」は、不正行為を正当化する心理的プロセスを指します。不正を犯す個人は、
自身の行動を倫理的または妥当であると考える理由を作り出します。
例1: 「給与が低すぎるから、これくらいは正当だ」と考え、現金を着服する。
例2: 「会社が大きな利益を上げているのだから、少しぐらい取っても問題ない」として備品を持ち帰る。
例3: 「この数字を操作しないと、部署全体が責任を問われるから仕方ない」として会計データを改ざんする。
報道や記者会見の内容を元に、今回の事案を「不正のトライアングル理論」に当てはめてみてみたいと思います。報道で明るみになっていないことも多いので一部は推測です。
【機会】
・スペアキーは封筒で管理
・確認ルールがあるが、詳細はなく曖昧になっている。
・支店長代理でチェックする側の立場
・女性行員1人での対応
※上記は報道されている事実で、
ここからは推測となります。
【動機・プレッシャー】
・投資で失敗しその穴埋めがしたい
(投資に流用していたと供述しているため)
【正当化】
・給与が上がらない。
(貸金庫業務は儲からないため)
・投資で増やして、あとから返せばいい
(投資に流用していたと供述しているため)
このように不正が発生しやすい条件が揃っていたのです。
ブランディング視点から観た今回の一連の騒動について
ブランドコンサルタントの視点から今回の騒動を見てみましょう。前提として、現状の三菱UFJ銀行のブランドの状態は「ブランド・マイナス」と言えます。
<ブランド・マイナスとは>
消費者顧客がブランドをみてネガティブな印象を頂いた時そのブランドの状態は「ブランド・マイナス」と言える。<ポイント>
その商品・サービスをブランドか、そうではないか、
ブランドの状態が良いか悪いかを判断する主体は、消費者顧客が主体である。
銀行ビジネスにとってブランドマイナスの状態は致命的
記者会見が開かれたのは、事件公表から24日たった12月16日でした。半沢氏はこの時期に会見を開いたことについて「被害に遭った顧客に対する補償のプロセスが始まり、貸金庫を今後も安心してご利用いただける対応策の実施にめどがたったためだ」と説明しています。しかし、ブランディングの視点からみるとこの対応の遅さは致命的です。
ブランディングと聞くと、「企業イメージをよくしたい」「新商品を売りたい」「モテたい」と言った、ブランドプラス(ポジティブ)を目指すために取り組む活動だと考える人が多いかもしれません。しかし、ブランドマイナスを避ける戦略も同じかそれ以上に重要なのです。なぜならブランディングとは、「顧客の企業に対するイメージ」と「企業が顧客のどう思われたいか(ブランド・アイデンティティ)」この乖離を埋める活動の総称だからです。
ブランドマイナスを防ぐことが優先される業種とは
ここで、ブランドマイナスを防ぐことを重視しなければならない業種や分野を紹介します。
【医療業】
・医療ミスがあった病院は不安だから行きたくない。
【生活インフラ業】
・停電が多いから電力会社を変えたい。
【ネットインフラ業】
インターネット回線がつながらずイライラする。
ネットが重いからサービスを変えたい。
【交通インフラ業】
電車が1分遅延したせいで遅刻し、怒られた。
皆さんも上記のような経験をしたことがありませんか。上記のように「あって当たり前」と感じてしまう業種やサービスは、1秒の遅れ、1度の問題が大きな不満・不信・不安に繋がってしまいます。今回の事件はどうでしょうか。「銀行はお金をまもってくれて安心。それが当たり前」「自分の資産が盗まれそうな銀行には預けたくない」と思った方も多いでしょう。銀行もまさにブランドマイナスを避けなければならない業種なのです。
不正のトライアングル・ブランドマイナスを防ぐためには
ブランドマイナスを防ぐための防止策については、前段で記述した「不正のトライアングル」をベースにするとよいでしょう。「機会」「動機」「正当化」に対応した防止策・戦略を立てることが不正行為防止に効果的です。
「機会」への対策
「機会」への対策は、3要素の中で最も取り組みやすい要素です。個人に動機や正当化の要素があったとしても、内部統制を整備し不正可能な機会をつくらないことで、不正の発生を大幅に軽減できます。
「動機」への対策
「動機」は個人の内面に関わるため、完全に排除することは困難です。しかし、「動機を持たせないための環境づくり」に取り組むことは可能です。
「正当化」への対策
「正当化」も、個人の内面や思考に関わるため、完全に排除することは困難です。しかし、「動機を持たせないための環境づくり」に取り組むことは可能です。

上記はあくまで一例ですが、このように整理することで精度の高い対策が可能です。SNSが当たり前に利用される現代において、不正や一瞬にして拡散されます。一挙手一投足が致命傷につながるリスクがあるからこそブランドマイナスを防ぐことがブランディングを進めるうえでも重要なのです。
CBOメディア&ラボ【ブランディング推進のための情報メディア】
【経営×ブランディングの責任者(CBO)を日本で増やす】経営に貢献する真のブランディングを広めるために、ブランドづくりの基礎知識・ポイントからさまざまな事例、そして実践的に学べるセミナー、相談会まで。幅広いメニューで社会にCBOを増やしていきます。
※一般財団法人ブランド・マネージャー認定協会公認
最新情報を発信しています。

■千田 新(ちだ あらた)執筆
クリエイティブアソシエイト・コピーライター